はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。
私がアシュタンガ・ヴィンヤーサ・ヨガ(以下、アシュタンガ・ヨガ)に出会ったのは2006年。呼吸と動作を連動させながら、決まった順番でポーズを行うこのヨガは、自主練習が基本で、ポーズは生徒の準備に応じて与えられるという特徴を持つ。
18年以上にわたりアシュタンガを実践し、インストラクターとしても活動してきた中で、私は次第に「ヨガだけでは届かない身体の層がある」と感じるようになった。それを埋めてくれたのが、ロルフィングというボディワークである。
ロルフィングでは、筋膜や構造に働きかけることで、ヨガのポーズではアクセスしにくい無意識的な身体の“使い方”を再教育する。一方、ヨガは意識的に身体を感じ取り、自分の内側と深く向き合う時間を提供してくれる。
この連載では、「ヨガの練習をより深め、怪我を防ぎ、プレゼンスを高めるために、ロルフィングの視点から何が学べるのか?」をテーマに、ヨガを実践する方に向けたヒントを全3回で紹介していく。

ヨガとロルフィングの架け橋・全3回・連載
第1回|身体地図としての構造と感覚
ポーズが“うまく取れない”のは、柔軟性だけの問題ではないかもしれません。
あなたの身体地図(ボディスキーマとボディイメージ)は、正確だろうか?
この回では、ロルフィングとヨガがどのように「身体の感じ方」と「動かし方」を再編成するのかを明らかにする。
第2回|呼吸がひらくプレゼンス──身体深層とのつながり
安定したポーズの鍵は、表層ではなく、深層の呼吸と支え(Tonic Function)にある。
身体が“自然に呼吸している”とき、意識は今ここにとどまることができる。
この回では、呼吸と構造の再教育を通じて、プレゼンスがどう育つのかを探っていく。
第3回|構造と感覚の再統合
ヨガのポーズを深める鍵は、柔軟性ではなく、身体の内側に“スペース”をつくることにある。
この回では、doing(やること)ではなく、being(在ること)から起こる変化に焦点を当てながら、ヨガとロルフィングの共通点である「スペースの知恵」を探っていく。
この3回の連載を通じて、「ポーズが深まらない理由」「呼吸が詰まる感覚」「左右差がなかなか改善しない悩み」といったヨガの実践現場で多くの人が直面する課題に対して、構造と感覚の両面からアプローチする方法を紹介していく。
特に、「もっと自由に動きたい」「自分の身体をもっと深く感じたい」と願う方にとって、ヨガとロルフィングの融合は、新たな視点と可能性を開いてくれるはずだ。
ヨガと身体地図〜ズレのサイン
ヨガの練習中ヨガの練習中に、こんな経験をしたことはないだろうか?
- 右側はスムーズなのに、左側だけ引っかかるような違和感がある
- 前屈で「伸びているつもり」なのに、写真を見ると背中が丸まっている
- 呼吸が胸のあたりで止まり、どうしても深まらない
- インストラクターの言葉は理解できるのに、身体が反応しない
これらは筋力や柔軟性だけの問題ではなく、「身体の地図」にズレがあるサインかもしれない。
この“地図”とは、私たちの動作や感覚を司る「ボディスキーマ」と「ボディイメージ」である。
ボディスキーマとボディイメージ──身体の“地図”を理解する
身体を「動かす」と「感じる」は別のレベルに存在している。 このことをわかりやすく整理してくれるのが、サンドラ&マシュー・ブレイクスリーの『脳の中の身体地図(The Body has a mind of its own)』という本だ。
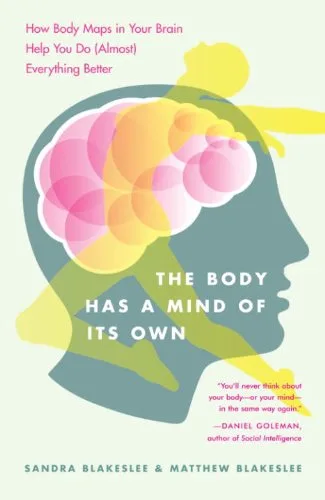
ボディスキーマとは?──無意識で働く“身体のOS”
“Your body schema is what allows you to scratch your head in the dark without having to look for it.”
— Sandra & Matthew Blakeslee, The Body Has a Mind of Its Own
ボディスキーマとは、無意識に身体を空間の中で動かすための神経的な地図である。
たとえば、目を閉じていても足の位置がわかる、暗闇でも頭を掻ける──こうした動作は、ボディスキーマの働きによって可能になっている。
ヨガのポーズの例でいえば、マットの上で目を閉じたままチャトランガからアップドッグに移行できるのは、スキーマが働いている証拠だ。逆に、バランスポーズでぐらつく、ねじりポーズで左右差が大きい、立ちポーズで軸が定まらない──それらは、ボディスキーマのズレが影響している可能性が高い。
この地図がずれていると、「自分では真っすぐ立っているつもり」でも、実際は傾いていたり、動作にムラが出たりする。ロルフィングは、この見えない地図を構造レベルから“再教育”するボディワークである。
ボディイメージとは?──身体を“どう感じているか”
“Body image refers to how the body feels from the inside — a sense of self located in and through the body.”
— Jeff Maitland, Spacious Body
ボディイメージとは、「自分の身体をどう感じているか」という主観的な感覚である。
「今日は足が重い」「胸が詰まっている」といった内面からの気づきは、ボディイメージに基づくものである。
ヨガでは、このボディイメージを育てることが非常に重視されている。ポーズや呼吸、瞑想を通じて、「内観する力」や「身体に耳を澄ます力」が養われる。
しかし、ボディイメージは主観的で曖昧な側面もあるため、思い込みや誤認が起こりやすい。そこで、ロルフィングでは、まずボディスキーマ──すなわち構造と無意識の動作パターンに働きかけることで、結果的にボディイメージにも変化をもたらす方法をとる。
ヨガとロルフィング──身体の“地図”を両側から書き換える
ヨガはボディイメージ(感じる力)を磨き、ロルフィングはボディスキーマ(動くための構造)を整える。
たとえば、マリーチアーサナCのツイストが深まらない場合。呼吸を意識してもなかなか可動域が広がらないとき、問題は“意識”ではなく“構造”にある可能性がある。背骨の並びや肋骨の位置、筋膜の滑走が制限されていれば、身体は防御的に硬くなる。
このようなケースでは、ロルフィングを通じて構造を整えることで、努力せずとも自然に動きが変わっていく。これはまさに、身体のOS=ボディスキーマが更新された結果である。
そして、それによって呼吸が広がり、感覚が明瞭になり、ポーズそのものへの印象も変化する──つまり、ボディイメージの質も変わっていくのだ。
身体は“世界とつながる媒体”──メルロ=ポンティの視点から身体地図を捉え直す
哲学者モーリス・メルロ=ポンティ(Maurice Merleau-Ponty)は、身体を「世界との関係性の媒体」と捉えた。
“The body is our general medium for having a world.” — Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception
「身体は、私たちが世界を持つための普遍的な媒体である」
それは、身体は単なる物質(オブジェクト)ではなく、私たちが世界に関わり、他者と出会い、環境と交わる“場”そのものであるという立場である。
この考え方は、ボディスキーマとボディイメージの両方の理解を深めるうえで重要である。身体を通して世界にアクセスしているという前提があればこそ、無意識の地図(スキーマ)と、主観的な感覚(イメージ)の両方が「知覚の条件」となる。
つまり、「ヨガを通して世界の感じ方が変わる」という体験──それは、単なる心の問題ではなく、身体の地図が更新された結果と言える。
まとめ:ヨガを深めるために、“見えない地図”を整える
- ボディスキーマ=無意識に動くための神経地図
- ボディイメージ=内側から感じる主観的身体感覚
- ロルフィングはスキーマを整え、ヨガはイメージを育てる
- 両者の統合が、プレゼンスを育み、より自由な身体へと導く
第2回は、呼吸と構造の関係を入り口に、“現象学的身体”とプレゼンスを深く掘り下げていく。
参考文献
- Sandra & Matthew Blakeslee, The Body Has a Mind of Its Own(邦訳『脳の中の身体地図』)
- Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception
- Jeff Maitland, Spacious Body, Embodied Being

