はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。

全7回・全体のご案内
今回は、ロルフィングとCTI(Co-Active Coaching)という、一見異なる実践が、いかにして「変容」という共通のテーマに向き合っているのかを、7つの視点から紐解いてきた。
- 【第1回】ニュートラルとプレゼンス
- 【第2回】4つのコーナーストーン
- 【第3回】3つのPrinciplesとロルフィング10シリーズの対応
- 【第4回】セッション間のプロセスの持ち方
- 【第5回】関係性の質(Designed Alliance / Right Relationship)
- 【第6回】スキルの比較(CTIの5スキルとロルフィングの技法)
- 【第7回】総括
各記事は独立してお読みいただけますが、全体を通じて読んでいただくことで、「触れる」「問う」「聴く」「在る」という「変容」について多面的に見えるようになると考えている。
共通点:違う手法、同じ在り方
ロルフィングとコーチングは、一方は身体を媒体とし、他方は言葉と対話を媒体とする。
しかし、どちらも以下の原則を共有している
- クライアントの中にある力を信じる
- 変化は「起こす」ものではなく、「起きるのを支える」もの
- プレゼンスと関係性が変容の本質を決定する
この意味で、ロルファーもコーチも、「何かをする人」ではなく、場を保ち、共に在る人であると言える。
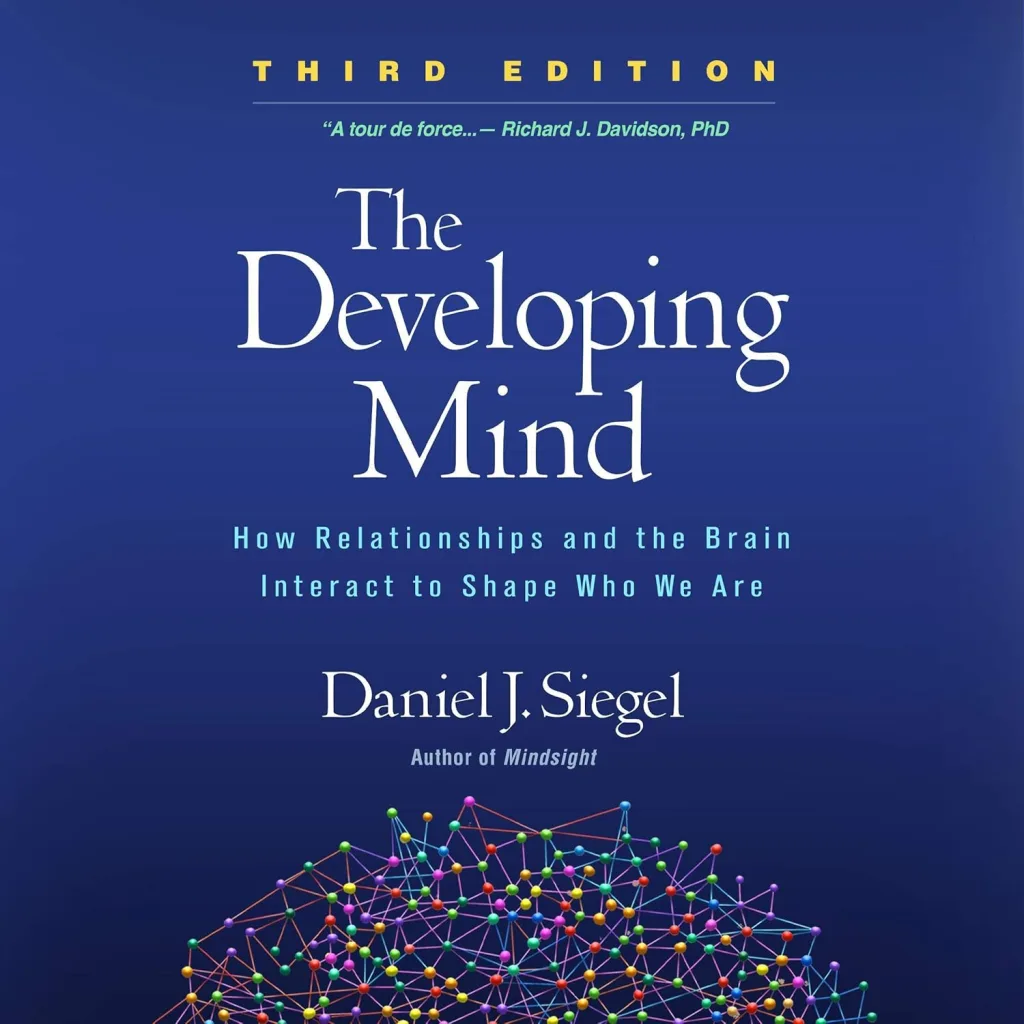
神経科学者であり精神科医のDaniel J. Siegelは、The Developing Mind(3rd edition)にて「統合(integration)」について以下のように述べている。
“Integration creates a flexible, adaptive, coherent, energized, and stable (FACES) flow of energy and information.” (統合とは、柔軟で、適応的で、首尾一貫していて、活力に満ち、安定したエネルギーと情報の流れを生み出す)
― Daniel J. Siegel, The Developing Mind (3rd ed., 2020)
この視点は、まさにロルフィングが身体の構造を、CTIが人の内的経験を、「分離からつながりへ」と導く共通の意図を持っていることを裏付けている。
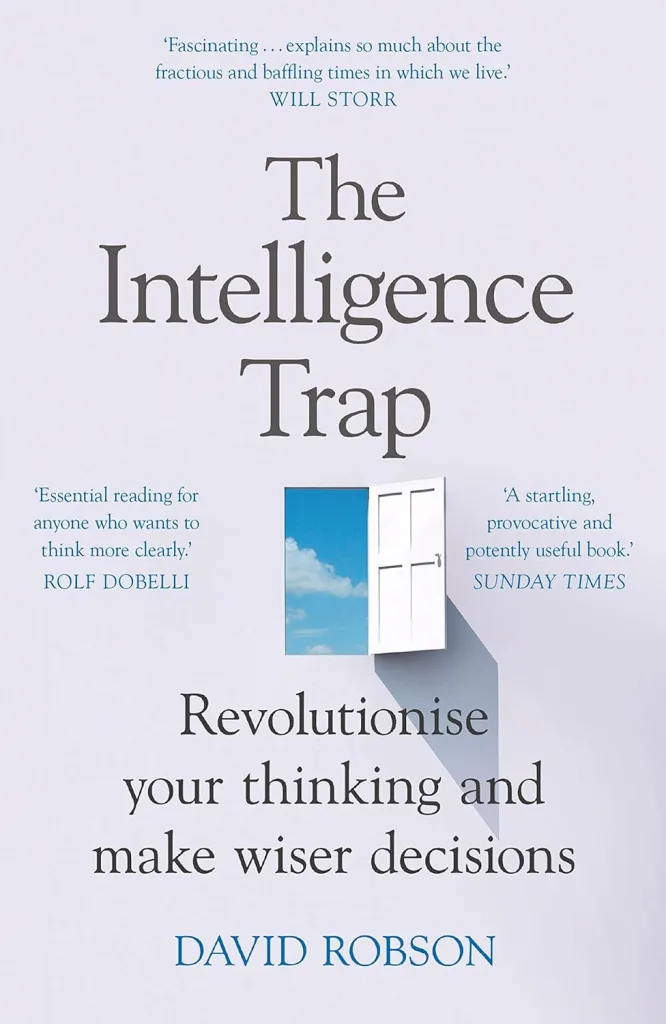
一方で、David Robsonは『The Intelligence Trap』において、知性とは単なるIQではなく、変化への柔軟性と自己修正の能力に根ざすという。
“Intelligent people can be blind to their own flaws if they lack the metacognitive skill to question their assumptions.” (賢い人であっても、もし自らの前提を問い直すメタ認知能力がなければ、自分の欠点に盲目になり得る)
― David Robson, The Intelligence Trap (2019)
これは、変容の場において「知っていること」よりも「開いていること」が重要であるという、ロルフィングとCTIの態度を支えるものである。
各回のまとめ
第1回:ニュートラルとプレゼンス
- ニュートラルとは「非操作・非干渉の深い関与」
- プレゼンスとは「空間全体に作用するBeingの質」
第2回:4つのコーナーストーン
- 人は創造的で、全体で、変化し続ける存在
- ロルフィングも身体を「秩序と可能性の場」として扱う
第3回:3つのPrinciplesと10シリーズの対応
- Fulfillment → Sleeve
- Balance → Core
- Process → Integration
第4回:セッション間のプロセスの持ち方
- CTIはForwardを明示して行動に落とす
- ロルフィングは余白の中で自然な変容を信頼する
第5回:関係性の質とセッション構造
- CTIは対話で関係性を明示的にデザイン(Designed Alliance)
- ロルフィングは非言語的な触れ方で信頼を育む(Right Relationship)
- セッション構造:CTIは Design → Explore → Forward /ロルフィングは Sleeve → Core → Integration
第6回:スキルの比較(CTIの5スキルとロルフィングの技法)
- Listening, Intuition, Curiosity, Forward/Deepen, Self-Management
- それぞれに対応する「触れ方」と「在り方」が存在し、実践例も紹介した。
言葉と身体、対話と触れ方の橋を架ける
この連載で明らかになったのは、ロルフィングとCTIは手段の違いを超えて、同じ哲学に根ざしているということ。
- コーチングは、身体性への言語的なアクセスである
- ロルフィングは、言葉にならない身体の対話である
両者が交わる点には、以下のような価値がある。
| 共通する本質 | コーチングの言語 | ロルフィングの身体性 |
|---|---|---|
| プレゼンス | 傾聴、沈黙、Being With | Listening Touch、空間保持 |
| 意図の放棄 | Fixしない姿勢 | Right Action、共鳴 |
| 信頼 | クライアントの資源を信じる | 身体の自己組織化を信じる |
誰に、どちらが適しているか?
この探究の中で自然と浮かび上がってきたのは、コーチングとロルフィングのどちらが今の自分に合っているのか?という問いだ。
以下にいくつかの指針を紹介したい。
コーチングがより適している人
- 内面の思考や感情のパターンを言語化して整理したい
- キャリアや人間関係の選択肢に迷っており、方向性を明確にしたい
- 会話を通じて自分自身とのつながりを深めたい
- 日常生活の中で「行動」に変化を起こしたい
ロルフィングがより適している人
- 言葉では捉えきれない身体的な不調・違和感を抱えている
- 姿勢や動き、呼吸などに変化を起こしたい
- 深いリラックス状態やプレゼンスを体験したい
- 身体感覚を通して「Being」にアクセスしたい
そして、多くの人にとって大切なのは、「今、どちらが必要か」を感じ取りながら、ときに両方を補完的に使う柔軟性なのかもしれない。
まとめ:私たちは「何をするか」より、「どんな場で共に在るか」によって変わる
変容とは、意図と行動、知覚と感受、思考と構造の統合された体験。そのためには、テクニックよりも「在り方」が求められる。
✨「触れる」とは、「共に居ること」。
✨「問いかける」とは、「相手の命に耳を澄ますこと」。
この全7回の連載が、言葉と身体、内面と外側、DoingとBeingの間に架け橋をかける一助となれば幸いです。
参考文献
- Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phillip Sandahl, & Laura Whitworth (2018). Co-Active Coaching: The Proven Framework for Transformative Conversations at Work and in Life (4th ed.). Nicholas Brealey.
- Jeff Maitland (2017). Embodied Being: The Philosophy and Practice of Manual Therapy. North Atlantic Books.
- Dr. Ida Rolf (1977). Rolfing: Reestablishing the Natural Alignment and Structural Integration of the Human Body for Vitality and Well-Being. Healing Arts Press.
- Daniel J. Siegel (2012). The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are(2nd ed.). The Guilford Press.
- David Robson (2019). The Intelligence Trap: Why Smart People Make Dumb Mistakes. W. W. Norton & Company.

