はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。
先週(2025年4月8日〜)から、東京の市ヶ谷で日本ロルフィング協会主催のアドバンスト(上級)・トレーニング(AT)に参加している(講師は、Ray McCallと田畑 浩良さんの2名)。3週間にわたって、火曜日〜金曜日に行われ、6日目(4月16日)を終えた。
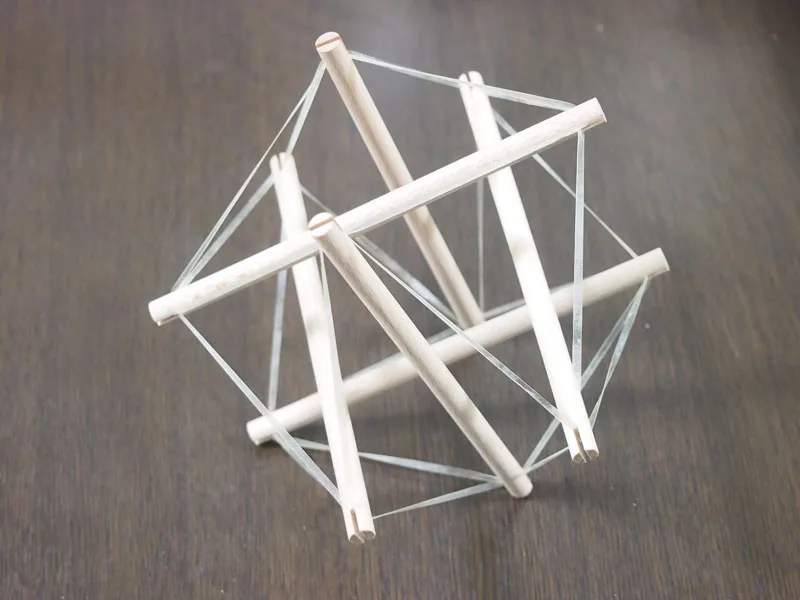
改めてAT取り上げられたのが、Jeff Maitlandがまとめあげたロルフィング理論のフレームワークだ。Jeffの思想を軸に、ロルファーにとって実践的に役立つ視点で紹介したい。
Jeff Maitlandとは?
Jeff Maitlandは、Purdue大学で哲学を教えたバックグラウンドを持つロルファーだ。
特に、現象学(Phenomenology)と禅の思想をロルフィングに取り入れたことで知られている。
彼の貢献は、単なる手順(Protocol)に頼るのではなく、
「原理・原則(Principles)」に基づくロルフィングを可能にした点にある。
Ray McCall氏は、次のように紹介た。
「Maitlandは、Ida Rolf博士が作った10シリーズを”脱構築”し、原理・原則へと昇華させた。」
5つの原理・原則(Principles)
Maitlandは、以下の5つの原理を整えた(最後のCLOSUREはPedro Pradoと共同提唱)。
- WHOLISM(全体性)
身体を部分ではなく、全体のシステムとして捉える。 - SUPPORT(支持)
構造が自己支持できるように促す。 - ADAPTABILITY(適応性)
環境への柔軟な適応を支える。 - PALANTONICITY(二方向性)
上下・内外など相反する力のバランスを見る。 - CLOSURE(完了・クロージング)
プロセスに「終わり」をもたらし、次の段階へ移る。
これらの原理を理解することで、
単なる手技ではない、「身体の統合」という大きな目的が明確になる。
なぜ「脱構築」が必要だったのか?
もともと、ATには、下記のアドバンスト・シリーズの手順(Recipe)が決まっていた。
- 身体軸(LINE)に戻す
- Zポジション、Cポジションに置く
- 膝・肘・肩のHINGEを整える
参考に、これを作ったのはIda Rolfではなく、Peter MelchiorとEmmett Hutchinsだ。
Ray曰く、
「この手順に固執すると、クライアントに負担をかけすぎる可能性がある。」
Maitlandはここに問題を見出し、「原理・原則に基づき、個々に応じたセッションを組み立てる(Non-Formulaic)」スタイルへと導いた。
観察力(Seeing)とは何か?
Jeffが最も強調したのが、「観察する力(Seeing)」を鍛えること。
重要なのは、
「単なる目視ではない。感覚器官全体を使って”身体を聴く”ことだ。」
彼は、Somatic Sensorium(身体感覚の総動員)によって情報を得ることを推奨した。
Rayも
「’Seeing with your own eyes’ は誤解を生む。身体全体で受け取ることが観察だ。」
と語っている。
- 見る
- 感じる
- 聴く
- 動きの質を受け取る
といった多次元的な感覚を活性化させることが、「観察力」を本当に育てる方法といえる。
ロルフィングのセッションでどう生かすか?
ATでは、セッションでこの考え方を生かすには、以下を意識するといいと学んだ。
Somatic Sensoriumを使って感じ取る
(”見よう”とするのではなく、”開いて受け取る”)
原理・原則を軸にセッションを組み立てる
(クライアントに必要なSupport、Wholism、Adaptabilityを見極める)
Protocolに縛られず、個別に応じた対応をする
(流れを固定せず、必要なことだけを行う)
まとめ
Jeff Maitlandがロルフィングにもたらした最大のギフトは、
「固定された型から自由になり、本質に立ち戻る道を開いたこと」
ということに気づかされたことだと思う。
手技のスキルを超えて、
- クライアントの中にある自己組織化の力を信じ、
- 自らの感覚を磨き、
- より深い「統合」へと導く。
私自身、このアプローチはあまり意識していなかったので、今後、この在り方をセッションの提供するプロセスで深めていきたい。
少しでもこの投稿が役立つことを願っています。
