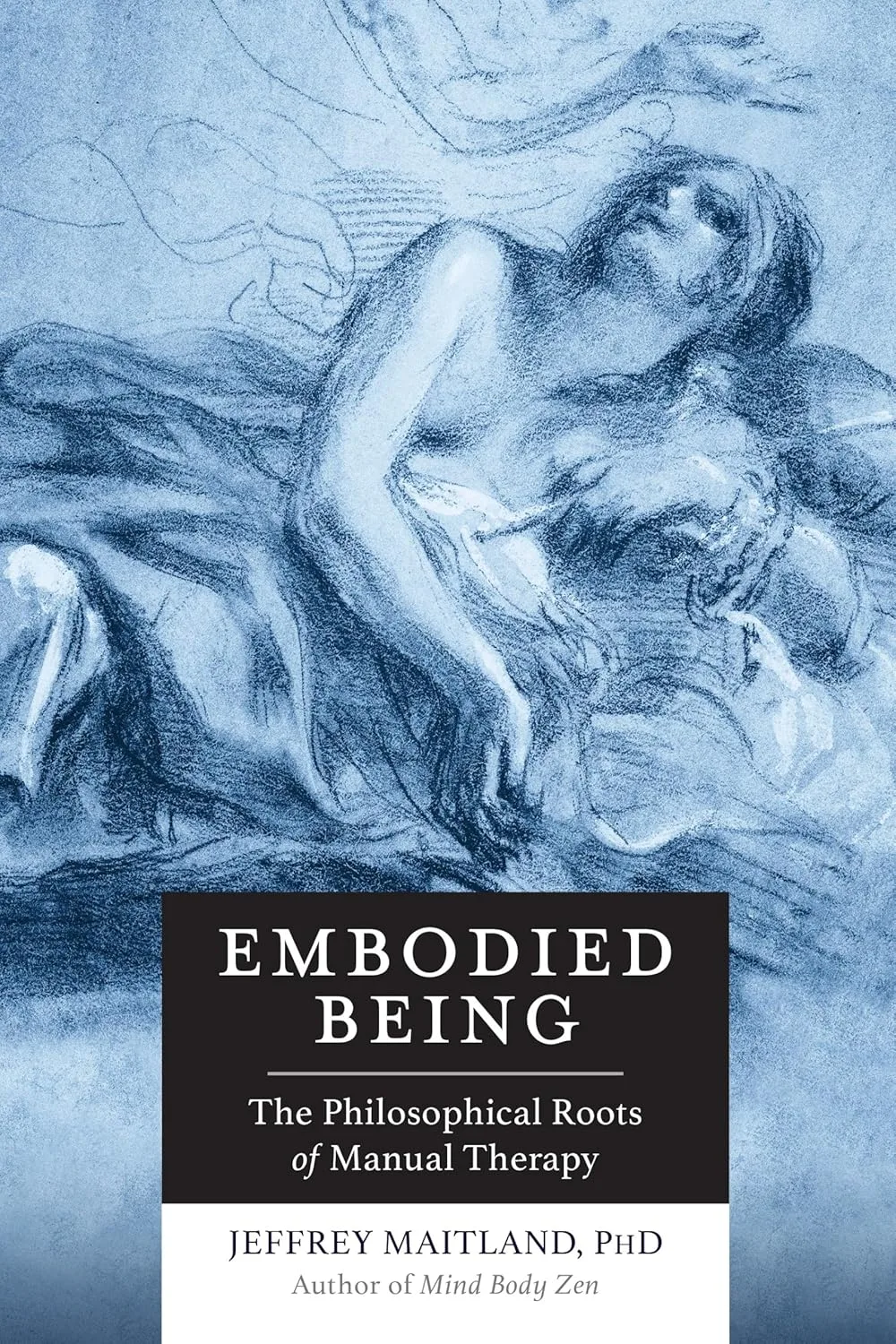はじめに
渋谷でロルフィング・セッションを提供している大塚英文です。
現在、アドバンスト・ロルフィングのトレーニング(Phase 2)の後半6日間を終えた。外部クライアントへのセッション、生徒同士での実践を通して、Ray McCall先生、田畑浩良先生からの深いフィードバックを受け取りながら、多くの気づきを得ている.
トレーニング期間中、Ray McCall先生のお勧めもあり、Jeff Maitlandの著書 Embodied Being – The Philosophical Roots of Manual Therapy (未邦訳)を手に取って読んでいる。
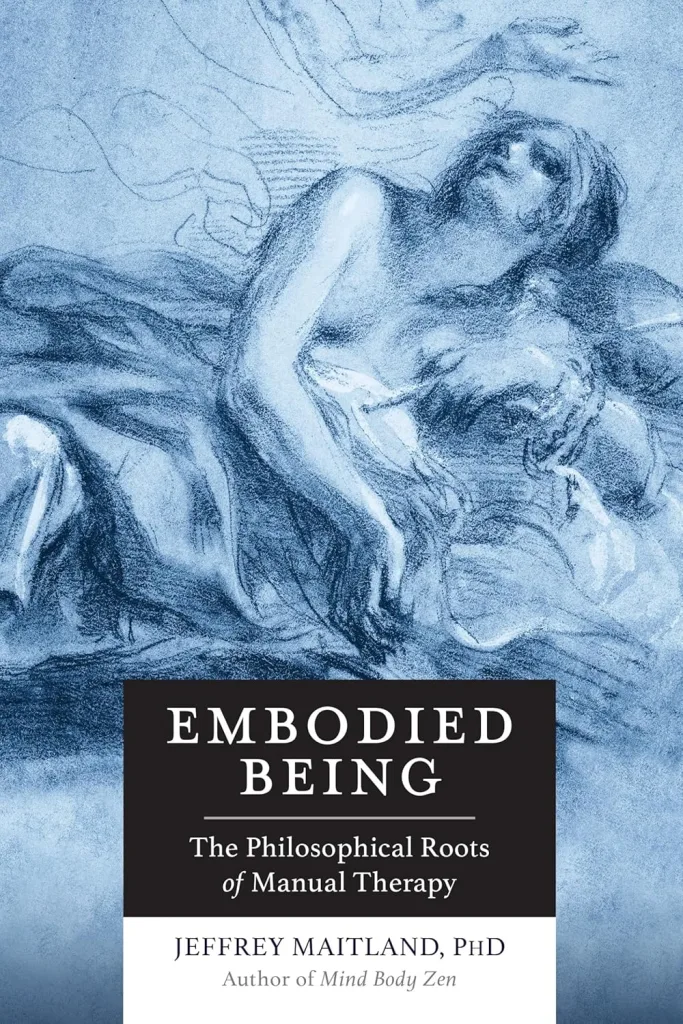
Maitlandは大学で哲学を教えていただけあって、ロルフィングを含むボディワークを提供していくということは、単なる技術体系ではなく、いかに深い哲学的・身体的探求であるかを改めて実感した。中でも、Rayがトレーニング中に紹介した、「Orthotropism(オーソトロピズム)」という言葉に強く心を動かされた。
今回は、その言葉を軸に、「なぜ中立性(Neutrality)が重要なのか?」を掘り下げてみたいと思う。
垂直性とは、身体が生きようとする志向性
ロルフィングの創始者のIda Rolf博士は、「身体はライン(line)を中心に構築されている」と語った上で、Jeff Maitlandは、Embodied Being の中で、その考え方を以下のように補足している
“Every inch of the body is striving to unbind its morphological potential by cultivating the vertical.”
身体のあらゆる部分が、その形態学的な可能性を解き放とうとしながら、垂直性(Verticality)を育もうと努めている。– Embodied Being, Jeff Maitland
この一文は、身体の姿勢の問題にとどまらず、身体が内的に「生きようとする方向」へ向かっているという本質を捉えている。
ここで登場する “orthotropism” という考え方は、ギリシャ語の orthos(正しい、まっすぐ、垂直)と tropos(向かう、傾く、傾性)を語源とする言葉。生物がある方向(ここでは“垂直”)に向かって成長しようとする傾向を表している。
ひまわりが光に向かって伸びていく“向性”(heliotropicと呼ぶ、helioは太陽)と同じように、人間の身体もまた、重力の中で垂直を求める性質を持っているという。
垂直性は「自己をつくる」活動
Maitlandは、人間の身体は、動物と共通する構造を持ちながらも、重力を垂直的に取り入れること(vertically appropriating gravity)で、自己を方向づけ、意識をもち、自らを形づくる存在へと進化してきたという。
更に、彼は、次のように語る:
“By vertically appropriating gravity, human morphology transforms these common animal structures and organizes them into an upright, self-directed, self-conscious whole.”
人間の身体は、重力を垂直的に取り込むことによって、動物と共通する構造を「自分自身を方向づける、意識をもった全体」へと変容させてきた。
ここでの重要な点は、「垂直性と意識は共に進化してきた(verticality and consciousness evolved together)」という考え方だ。
垂直に立つ(=直立二足歩行)は、生きることそのものと不可分であり、意識と自己形成の基盤でもあると言ってもいい。
感じている身体(sentient body)と soft machine の違い
このような身体観は、私たちがしばしば捉えがちな「身体=機械」という考え方とは一線を画します。
Maitlandが繰り返し使う “sentient body” という表現は、感覚し、感じ取り、反応し、自らを知覚する身体(sensing self)を意味する。これは、外部から操作される「soft machine」としての身体観、つまり身体と心を切り離して考える、ルネ・デカルト的な二元論(主観と客観を分けて考える)とは根本的に異なる視点だ。
それは、現象学(Phenomenology)的な視点、特に、モーリス・メルロ・ポンティ(Maurice Merleau-Ponty)が提唱したように、身体とは主観でも客観でもなく、それらを同時にはらんだ「生きられた身体(le corps vécu)」であり、世界との関係性の中で立ち現れる存在として捉えることを意味する。
“When we speak of the body’s verticality, we are not simply referring to the body as an object, but to the orthotropic activity of the sentient body.”
垂直性を語るとき、それは単なる“物体としての身体”ではなく、“感じている身体”が行うオーソトロピックな活動である。
この理解こそが、ロルフィングにおけるタッチの質、セッションのあり方、そして「中立性」の意味を一変させることへとつながっていく。
中立性とは、身体の「整う力」に委ねること
このように、身体が自ら垂直を探し、自己を形づくろうとする性質をもっているからこそ、ロルファーを含むボディワーカーに求められるのは「何かをすること」ではなく、「相手に委ねること」が重要になってくる。
“By working this way, we are tapping into the self-organizing, self-making, reflexive, self-shaping orthotropic nature of our client.”
このように働きかけることで、私たちはクライアントの中にある「自己組織化し、自らを形づくろうとする力」に触れることができる。
中立性とは、「空っぽでいる」ことでも「無関心」ではない。
それは、身体が本来持つ「整おうとする力」「重力と協働しようとする力」を信頼し、繊細に寄り添う姿勢。
この態度の中にこそ、ロルフィングの本質があると感じる。
Rayは、ロルファーの在り方として以下のように表現している
“benign indifference”(優しい無関心)
これは、施術者が「相手を変えようとしない」「判断せずに関わる」「結果をコントロールしようとしない」あり方を表す言葉で、Neutrality(中立性)を端的に表している言葉のように思う。。
“benign” は「優しい、穏やかな、害を与えない」、
“indifference” は「無関心、距離を取ること、執着しないこと」
この言葉は、ただ“何もしない”のではなく、信頼をもって距離を取ること、整おうとする相手の力を邪魔しないことを意味している。
おわりに:関係性とプレゼンスの中で
Phase 2の折り返しを迎え、あらためて感じるのは、ロルフィングとは「テクニックの巧拙」よりも、「関係性の質」「プレゼンスのあり方」「重力との協働」に深く根ざしているということです。
Orthotropismという言葉は、単なる解剖学的な事実ではなく、「身体が生きようとする志向性」を表す深い哲学でもある。
そして、その力に寄り添うために必要なのが、「中立性」なのでしょう。
少しでもこの投稿が役立つことを願っています。